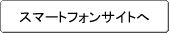|
2023/1/27
|
|
金融機関が金融教育(笑)する愚かさ! |
|
|
今、岸田政権のもとで、「貯蓄から投資へ」という流れが加速している。そのためにNISAの拡充等の施策が進められており、大変結構なことである。 しかしその一方で、その流れに悪乗りし、健全な資産形成という目的に逆行する動きも進んでいる、金融機関による金融教育と称するものだ。 1 金融機関といってもピンからキリまであるが、ザックリ分けて銀行&証券の2種類に分かれる。 2 1997年の金融ビッグバンまでは、銀行 = 貯蓄、証券 = 投資、というすみわけがなされていた。 銀行 = 低金利の預貯金を集め、それを原資として高金利で貸し出し、利ザヤ収入を得る。 証券 = 投資商品を販売し、その販売手数料&保有手数料で収入を得る。 3 金融ビッグバンにより、銀行においても投信等の投資商品が売れることとなった。 4 バブル崩壊以降の景気低迷により、利ザヤ収入は激減し、銀行は投資商品販売に血道をあげることとなった。 5 当然ながら、本家本元である証券業界も座して見ているわけにゆかないので、これまた今まで以上に投資商品販売に力を入れることとなった。 一 貯蓄 = 元本保証かつ確定金利商品であり、預金者&金融機関はウイン・ウインの関係である。我が国においては資産形成はこれが主流であった。 二 投資 = 金融機関の収入源は手数料収入である。 つまり、高い手数料 = 会社儲かる&投資家損する、という真逆の関係であり、このことを「利益相反」という。 三 2022年より、高校において金融教育が教えられることとなった。また昨今では大学生やサラリーマン向けの金融教育も行われている。 問題は! その金融教育なるもの、誰が教えているかということなのだが、なんと大半は金融機関やその業界団体が行っているのだ。 前述したように、貯蓄偏重の時代なら、銀行がそれを行ってもまあよろしかったかもしれない。しかし今やほぼゼロ金利の時代にあっては、投資こそが資産形成の大道なのである。 そして投資の世界においては、金融機関=高い手数料の商品を売りたい VS 顧客 = 安い手数料の商品を買いたい、というわけで、まさに敵同士なのだ。 そのような時代にあって、金融機関が国民相手に金融教育を行うなどというのは、カモ打ち漁師がカモに対し、「ネギをしょって私の前に来なさい」と言っているようなものだ。 ①こんなバカげたことを、平気で行っている学校・文部省&それを看過している金融庁の頭の構造を疑う。 ②1月25日付の日経には、某金融機関が国民相手に金銭教育のテストをして、国民の金融スキルを上げる、などという寝ぼけた記事が、なんと一面ぶち抜きの広告記事であった。 この会社名というのが、〇〇銀行コンシューマーファイナンス。 コンシューマー(消費者)ファイナンス(金融)、なんてことない、日本語に訳すれば消費者金融会社、昔のサラ金である。 桁外れの高金利で国民から多額の資産を収奪してきたサラ金がだよ、「金融教育」(笑)! 「プーチンがウクライナ国民に平和を説く」、あるいは、「習近平が中国国民に民主主義を説く」くらいの出来の悪いブラックジョークとしかいえない。 ③情けないことに、広告収入に目がくらみこんな記事を載せる新聞社や、これらの行為になんの疑問も持たない他の新聞社・テレビ局等々、まさにマスゴミの面目躍如というしかない。 心ある国民各位におかれては、間違ってもゼニゲバ漁師&マスゴミにダマされることなく、正しい金融知識を身に付けられんことを、切に願うものである。 、 |
|
| |