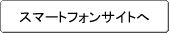|
2020/7/8
|
|
金融庁が動き出した! |
|
|
「投信・保険 リスク透明化。金融庁が提案」(2020.6 日経新聞記事より) 上記のように、金融庁は金融商品の販売において、顧客がリスクを理解できやすいようにするため、共通のルールを作るための指針を発表いたしました、以下ポイントをご説明いたします。 1 全ての金融機関共通の書式とする。 2 外貨保険で問題となっている、円高による元本割れの可能性を判りやすく伝えることとする。 3 銀行が、保険会社や証券会社から商品の供給を受けて販売する(金融仲介)際の、銀行が受け取る手数料を明示する。 この結果、いわゆる利益相反的なものを顧客が判断できやすいこととなる。 すなわち、 高い仲介手数料を取る金融商品の販売 = 銀行儲かる ↔ 顧客損する まだ検討段階ですが、2021年導入を目指すとのことであります。 私が当ブログで再三述べているように、金融機関というのは、「資産運用商品を売る(すなわち、手数料を稼ぐ)プロ」であって、「資産運用を手伝う(すなわち、顧客の資産を増やす)プロ」ではないのであり、であるからこそ、彼らは上記のような己に都合の悪いことは、積極的に説明せず、書面においても虫眼鏡で見なければ見えないような小さい文字でしか、記載しないのであります。 この制度が一日でも早く実施されることを期待すると同時に、それに至るまでに注意すべきことも改めて述べてまいります。 ①老い先短い高齢者に、外貨建て保険を売りつけるなどというのは、犯罪ではないが、犯罪的行為である。 ②保有時の手数料が年0.5%超の商品を買うのは、どぶに金を捨てるようなものである。 (仮に、その商品が短期的に好パフォーマンスを展開していたとしても) ③「運用報酬」「運用手数料」「管理手数料」等の名目で、②以外の保有手数料を取る商品を買うのは、どぶに金を捨てたあげく、業者に中元と歳暮を毎年あげているようなものである。 結論:うまい話や、おいしい話には、必ず裏がある。 貴方が頼るべきは、どこの会社にも属さず、どこの会社からも(商品販売にかかる)報酬を受けていない、独立ファイナンシャルプランナーである。 |
|
| |