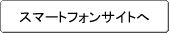|
2022/7/3
|
|
カモネギ教育を憂う! |
|
|
「カモネギ」という言葉をごぞんじだろうか? 鴨がねぎを背負ってやってくる、という言葉の略語であり、その意味するところはこうだ。 1 漁師が鴨鍋用に、鴨を打ちに行く。 2 鴨鍋はそれ自体でも美味いが、それにねぎを加えればなお美味い。 3 ところで、鴨は鉄砲で打てば手に入るが、ねぎはその後八百屋へ買いに行かねばならない。 4 ところが、驚くべきことに鴨がねぎを背負って飛んできたのだ。 5 鴨を打つだけで、ねぎも一緒に手に入るという、一挙両得のお話である。 ところでこの話、実際に漁師の三太郎さんが経験したことを得意げにしゃべった、ということではない。 漁師(詐欺師)が待ち構えているところへ、のこのこ鴨(詐欺被害者)がねぎ(お金)を抱えて、やってきた(くる)ということのたとえ話であり、このようなことにあってはならないという警告、戒めのための寓話である。 ところが今、この寓話が寓話ではなく、現実にしかも教育の現場で行われているのだ。 このほど、国(文部省)の方針で、学校教育の中で金銭教育を取り入れることとなった。そのこと自体はよろしいのだが、問題はそれを行う教育者の人選だ。 教員・職員の中でそれを行えることのできる人は多くない。外部に依頼することとなるのだが、その大半が金融機関(の社員)なのだ。 金融機関(銀行、証券会社等)の主たる収益源は以下二つだ。 一 顧客から預かったお金(預金)を、貸出に回し、その利ザヤを収益とする。 この場合、預金は元本保証・確定金利を手に入れ、銀行等は貸出利益を得る、両社とも利益を得る「ウイン・ウイン」の関係である。 二 顧客に株式や投信等の投資商品を売り、売買手数料や信託報酬といった手数料収入を得る。 顧客は1円でも手数料の安い商品を買った方が得であり、一方銀行等は1円でも手数料の高い商品を売りたい。すなわち両者の利害は対立する「利益相反」の関係となる。 金銭教育において、銀行等が金融の基本的知識を教えることは悪いことではないが、しかしその程度のことは彼らに頼まなくても、教員・職員で十分にできる範囲のレベルである。 問題は、明らかに利益相反関係になる投資について、銀行等が講義をするということである。これって、投資セミナーで詐欺師が被害者(予備軍)に対し、しゃべっている構図と瓜二つだ。 このような、高校生を「カモネギ」に仕立てるようなことを、しかも国、学校が先頭に立って行うなどというのは、正気の沙汰ではない、愚鈍な企みというほかない。 金銭教育を行える人材は、我が国においてただ一つの職種しかない。 どの金融機関のも属さず、どの金融機関から報酬を得ることのない、真に独立した金融の助言者、独立ファイナンシャルプランナー、ただ1種である。 国の間違い、世間の流れに惑わされることなく、一人でも多くの国民が正しい資産形成・・資産運用を行うことを切に願う次第である。 |
|
| |