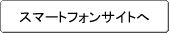|
2022/11/8
|
||||||||||||||||
資産形成の基本 |
||||||||||||||||
|
資産形成において、投資や投資商品について述べてきました。これからもそうなりますが、これは言うならばお金を増やす、すなわちプラスの方向の話であります。 大前提として、減らさない、すなわちマイナスを減らす三つの基本について述べたいと思います。 1 税金を減らす 世帯主(扶養者)が、収入が一定額以下の配偶者(被扶養者)を扶養している場合、給与所得において配偶者控除が適用される。 一 被扶養者については、一般的に「専業主婦」を指す場合が多いが、男性であっても構わない。 二 被扶養者要件は、年収103万円未満であること。 三 扶養者の所得から、配偶者控除(48円)が控除される。つまり扶養者の全収入が48円少なかったともなされ、その額に対応した税金が引かれる(戻ってくる)。 扶養者の年収によってその額は異なるが、例えば10パーセント程度もどってくるとすると、年5万円節税になる。 2 公的保険料を減らす 扶養者が給与所得者(いわゆるサラリーマンの場合)の場合、その人の加入する健康保険の被扶養者に含めることができる。 一 ①公務員等の場合 共済組合建保 ②企業または、業種の場合 健康保険組合建保 ③ それ以外 健康保険協会建保 二 被扶養者は、 ①年収130万円未満であること。 ②一定程度以上の障碍者及び60歳以上の方については、180万円未満であること。 三 扶養者の健保に入ることにより、被扶養者は自分の健保から脱退することとなり、その分の保険料が浮く、例えば年50万円保険料を払っていたとしたら、50万円節約できることとなる。 3 私的保険料を減らす 私的保険、具体的には生命保険、医療保険、損害保険の保険料を減らす。 一 生命保険 ①被保険者が亡くなることにより、その人の収入によって生計を維持していた方が、生活に困らないように、一定程度のお金を準備する。 ②したがって、そのような要件に合致しない方は、当然ながら入る必要は無い。 ③種類
ポイント 1 定期保険は定期、すなわち「有期保険」である。決められた期間、年齢の間に死なないと保険料は全額パーとなる。 2 養老保険は、図を見るとお判りのように、生存・死亡どちらの場合も保険金がおりる、いわゆる「貯蓄保険」である。 3 人間は必ずいつかは死ぬわけで、終身保険こそは、生命保険の基本の基本というべきものである。 以上の特徴を吟味したうえで、各個人がそれぞれの事情にあった保険を選ぶべきである。 二 医療保険 新聞広告や、テレビコマーシャル等で宣伝しているもので、「〇〇歳からでも入れます」なんていう文言を目にした(耳にした)方もあると思う。 ところで前段の2で述べたように、我が国は全国民がどれかの健康保険に加入している、「国民皆保険」の国である。 多くの国民は、これを当たり前のことと感じていると思うが、そんなことはない。米国をはじめ公的健康保険のない国など世界ではざらであり、仮にあったとしても我が国ほど優れた国はない。 例えば大きな病気にかかり膨大な医療費を支払う場合があるが、この場合、「高額療養費制度により、かなりの額が返金されるのだ。 ここまで書けばお判りと思うが、我が国において医療保険なるものに入る必要性はほぼゼロである。 医療保険、「ワルが作り、アホが入る」と覚えていただければよろしい。 三 損害保険 損保については、基本的に生保と同様である。それぞれの方が、それぞれの事情に合わせて入る(入らない)ことを、決めればよろしい。 人生において必要なお金はけちることなく使うべきだが、そうでない無駄なお金は使うべきであはない。 そして、国家が運営する税制・社会保障制度を正しく利用し、もらえるものはもらう、このことを今から実践していただきたい。 結果浮いたお金ができたとするならば、それを貯蓄プラス投資に振り向け、豊かで幸せな人生を歩まれることを、強く希望いたします。 |
||||||||||||||||
| |