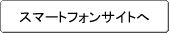|
2020/6/27
|
|
小学生でもわかる投資の基本 4 |
|
|
小学生でもわかる投資の基本、その最後の最後は、複利効果の説明です。 3 長期複利で運用すれば、資産は大きく増える。 二 「複利は、人類最大の数学的発明である」(A・アインシュタイン) 「複利」という言葉は、多くの方がご存じだと思います、表題通り小学生の段階で習うかどうかはともかく、おそらく義務教育の段階では教わることと思います。 例1:小さな雪の固まりを、資産の元本とみなし、 転がしながら付いてくる地面の雪を、利息とみなすならば、 最終的にできた大きな雪の固まりが、元利合計である。 と書けば、判りやすいかと思います。 例2:毎月3万円を、40年間、利回り5%で運用したとすると、 単利運用の元利合計額 = 1512万円 複利運用の元利合計額 = 4320万円(約3倍!) 言葉で説明する必要がないほど、明々白々たる違いであります。 同じ金額を、同じ年数、同じ利回りで運用しても、これだけの違いが出るということであり、前掲のアインシュタイン氏の言葉の重みが、ひしひしと胸に響きます。 余談ですが、 アインシュタイン氏は、ノーベル賞を取った正真正銘の天才ですが、ノーベル賞受賞者の全てが、皆天才というわけでは、ございません。 特に、戦後できたノーベル経済学賞という賞、これがまたスットコドッコイな代物でありまして、例えば1997年に米国のマートン&ショールズという二人の学者が受賞しました。 授賞理由が、デリバティブという、高等数学を駆使したリスクヘッジ理論(笑い)だそうであります。 ところで、翌1998年、この二人が理論を実践すべく経営に参加していた「LTCM」というヘッジファンドが、ものの見事にずっこけ、大損失を抱え倒産したのです。 その理由が、「ロシア通貨危機を予測できなかった」(大笑い)というのですが、おいおい、そういう危機をヘッジ(軽減)するための理論だろ(大爆笑)てなもんです。 というわけで、ノーベル賞学者といっても、まあこの程度のものです。 ちなみに、私はこの二人を、「脳減る(ノーヘル)経済学賞」受賞者と呼んでいます。 コロナショックで世界の市場が大暴落したわずか三か月前、我が国においても学者屋や評論屋が、「戦後最大の危機」だの、「当分相場は回復しない」等、寝ぼけた妄言をまき散らしました。 これに対し私は、「相場は必ず回復する」「今は、今世紀最大のバーゲンセール」だと、当ブログで記しました、結果どちらが正しかったかは、ご存じの通りです。 結論:資産形成の世界で信ずるべきは、人類最高の投資家であるW・バフェット氏 及び 人類最高の科学者であるA・アインシュタイン氏のみなり。 |
|
| |