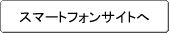|
2021/9/5
|
|
日本、米国、シナ Ⅱ |
|
|
前回、2021年秋における日本の現状について、述べました。 要約すると、 ①スルガ銀行を始めとするゴミ地銀を中心とした住宅担保ローンが息を吹き返しつつある。 ②ほぼゼロ金利という経済情勢の中、高金利で投資家を集めるソーシャルレンディングなる怪しげな金融商品が跳梁跋扈し、元本の9割棄損などという、ふざけたファンドも出てきている。 ③そんな中、世界最大のソブリン・ウエルス・ファンド(国家の富を増やす基金)であるGPIFは、REIT(不動産投資信託)に投資を始めた。 もちろん投資であるから、その保有割合や価格には十分注意すべきであるが、分散投資という観点からは好ましい方向である。 2 米国 そんな中、米国においてはどんなことが起きているかというと、 「米国ETF、選別型が主流に」(9・3 日経)という記事が出ました。 一 インデックス型が主流だったETFにおいて、昨年以降アクティブ型の上場がインデックスを上回るようになtった。 二 その要因は株価の上昇であり、このような時期には、個別株投資やアクティブ型投信の方がパフォーマンスが良くなる。 三 さらには規制緩和により、日々の銘柄を開示しなくてもよくなった。このことにより、運用会社はよりダイナミックな運用ができることとなった。 以下、三つのポイントについて述べたいと思います。 ア 米国においてETFはすでに金融商品の大きな一角となっており、個人投資家のみならず、年金等の公的投資家の購入も増えている。 イ というわけで、我が国において日銀がデフレ脱出のためにETFを買うというのは、しごく当然のことである。 にもかかわらず、このことを「官製相場」などと批判する立民党が、反資本主義・反経済成長・反繁栄の立場であることは明らかであり、絶対にこのような党に票を入れてはならない。 何故ならば、そのことは国民の富を減らし、貧困を増やし、失業者・自殺者を増やす、悪夢の道につながるからである。 ウ 私自身はインデックス推奨派であるが、アクティブETFが増えることは、そのこと自体は否定するものではなく、個々の投資家が自己責任で購入すればよいと考えている。 ただし、中長期的には、必ずインデックス型投信が勝利するであろうことは、信じて疑がわないものである。 次回は、隣国シナの現状と、このことをふまえた世界及び世界投資の見通しについて、述べてまいります。 、 |
|
| |