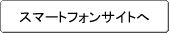|
2022/9/16
|
|
資産形成における学習と教育2 |
|
|
上記の題名で前回、投資勉強会について述べ、勉強すること自体はよろしいが、その対象が個別株投資となると、それって昭和の時代の話じゃないのということを記した。 1 金融リテラシー、心理面に注目を(9.14日経) 日経に「私見 卓見」というコーナーがあり、それへの投稿記事だ。 金融教育家として21年間、お金と心理の関係について観察してきた、と称する筆者が、結論として述べているのが、「お金の問題は知識だけでは根本的に解決できないという現実だ」と。 マジか?今問われているのはそんな抽象的なことではなく、資産形成に関する中立的かつ具体的な知識の教育がなされていないことだと、私は思いますがね、例えば。 2 高校で金銭教育、金融会社社員が講師 今年、2022年から高校における金銭教育は正式に義務化されたが、このことはそれより前の新聞記事である。 この金融会社なるもの、実は「〇〇コンシューマーファイナンス」という会社名であります。 〇〇は、大手メガバンクの名称、つまりその子会社なのだが、コンシューマーファイナンスなるカタカナ語、日本語に訳すれば「消費者金融」すなわちサラ金のことですよ。 最高裁の利息制限判決により経営が厳しくなったサラ金各社が、メガバンクの子会社となり、カタカナに名前を変えた、ただそれだけのことであり、やっていることは従来のサラ金そのものです。 これから社会に出る高校生相手に、サラ金の社員が「金銭教育」をするなどというのは、ブラックジョーク以外のなにものでもない、泥棒に防犯教育の講師をさせるようなもであります。 3 銀行協会、証券業協会が講師派遣 2で述べたように、今年から正式に金銭教育は始まった。さすがにサラ金社員が講師をするなどというバカな話はなくなったが、代わりに来るのが銀行・証券業界とは、五十歩百歩の世界だ。 金融会社 手数料の高い金融商品を売り儲けたい 顧客 手数料の低い金融商品を買い、無駄な出費を抑えたい。 見れば一目瞭然、両者の利害は真逆、いわゆる利益相反の関係だ。このような関係を知らない(わからない)文科省や学校が、なんの疑問ももたずっこれらの人間を講師として呼び、くだらない授業をしている、というのが悲しいかな現状である。。 資産形成を行うためには、最低限の知識・スキルが必要である。問題はそれをどのような方法で身に着けるかということである。 どの会社にも属さない、どの会社からも収入を得ない純粋な独立の金融専門家であり、かつ 国家資格っであるファイナンシャルプランニング技能士の資格を持ち、かつ投資実績&アドバイス実績のある、「独立ファイナンシャルプランナー」こそが、唯一正しい試算形成教育を行うに値する者であることを最後に記し、この文章を終わりたいと思います。 |
|
| |