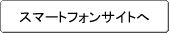|
2023/10/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税と社会保険のk基本、そして資産形成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税と社会保険の基本的数値について述べる。 単位:万円 青字:未満 赤字:以上 1 税
一 配偶者控除&特別控除 会社員(国民年金の第二号被保険者)の被扶養配偶者(第三号被保険者配偶者)たる妻(夫)の年収が一定未満ならば、夫(妻)の所得税額が減るメリットがある。 二 ザックリ言うと、我が国では年収200万円を超えると税負担が跳ね上がるデメリットがある。 三 ドーデもいいが、なんで195万だの204.4万などとい中途半端な金額なんだ?全く我が国の役人&政治屋はアホばかりだな。 2 社会保険
一 この表、もともとは130万未満&超というシンプルなものだった。 二 法改正により、3区分のやこしい表になった。改正の理由は社会の変化に合わせたもので、それ自体は評価すべきだ。 三 以下、具体例(概数) ①今まで年収105万円(手取り額)の人が、年収106万円を超えると、 106 - 10万円(厚生年金&健康保険保険料) = 手取り96万円、つまり年10万円近い減収となる。 ②手取り額を回復するためには、年収を125に増やし、 125 - 20(保険料) = 手取り105万円となる。 ③つまり、今まで並みの収入を維持するためには、年間20万円収入を増やす必要がある。 目安としては、一日1時間勤務時間を増やせばなんとかなる。 ④これからが最大のポイントとなる。 厚生年金の被保険者となることにより、一時的に手取り額は減る。ところで公的年金というのは税と根本的に違う、負担に対応した給付が約束されているのだ。 65歳以降厚生年金を受給することにより、だいたい10年くらいで今までの負担額を超える、つまり75歳が損益分岐点というわけだ。 人生100年時代、75歳以降ずっと一定額の年金を貰える、こんな素晴らしいことはない。 3 結論 男子であれ女子であれ、既婚者であれ未婚者であれ、日本人であれ外国人であれ、一人一人が自己責任で人生を切り開いてゆく時代である。 そして、そのような状況に合わせ国家は税、社会保険、資産形成について、国民の役に立つ制度をちゃんと用意している。 働き、稼ぎ、資産を増やそう。 iDeCoやNISAといった国の制度を使い、人類の進歩と共に発展するインデックスファンドを、ネット証券をはじめとする低コスト金融機関で運用する、これこそが21世紀における資産形成の大道であります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |